ドイツ・日本の異文化紹介 5 : 工場で選ばれる“ドイツ流オーバーシューズ”とは?
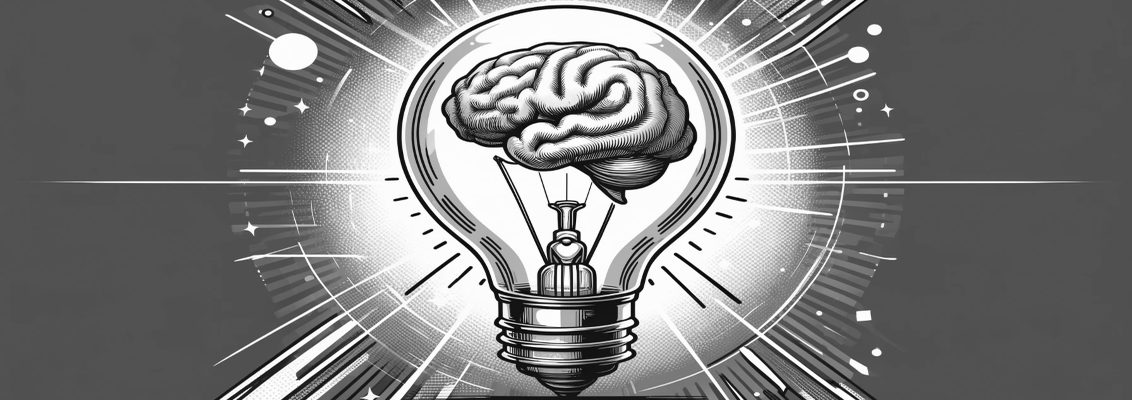
ドイツでは、来訪者や一部工程で“普段の靴の上から履く”オーバーシューズ(ヒールカップを持たない開放的な形状のものも含む)が浸透。一方、日本では JIS 規格の「安全靴」や JSAA 規格の「プロテクティブスニーカー」が主流です。両国の規格・運用の違いを理解すれば、ドイツ製安全靴の選定ポイントがクリアになります。HELUKABEL はドイツのケーブルメーカーとして製造業の安全・生産性向上を支える立場から、現場目線でわかりやすく解説します。
まず押さえたい「規格」の違い(EU : EN ISO 20345 vs 日本 : JIS/JSAA)
- EU(ドイツを含む)では、安全靴は原則 EN ISO 20345 に基づきテストされ、つま先保護 200J・滑り抵抗などの基準を満たすことが求められます。性能の組み合わせでSB, S1, S1P, S2, S3, S4, S5 といったクラス表記が使われます。現場でよく選ばれるのは耐貫通(P)や耐水性を含む S3 です。
- 日本では、革/ゴム/高分子靴の材料区分と、超重作業(U)/重作業(H)/普通(S)/軽作業(L)などの作業区分で定める JIS T 8101 が中核。これとは別に、合成繊維アッパー中心の JSAA規格(プロテクティブスニーカー)も普及しています。
ドイツで見かける“オーバーシューズ”という選択肢
- ドイツの工場では、**来訪者や短時間作業向けに、普段の靴の上から被せる「安全オーバーシューズ」**が広く使われます。つま先保護付きで、通常の街靴の上から簡単に装着できるのが特長です。
- 代表例として、Visitor/Visitor Protect 系のオーバーシューズは、滑り抵抗やアルミ/チタン合金製トゥキャップを備え、ISO 20345 試験項目に準拠した製品もあります(モデルにより仕様は差異)。
- ただし重要な注意点として、一部のオーバーシューズは「つま先保護部材(EN 12568)」の試験のみで、フル装備の EN ISO 20345 安全靴としては認められないケースがあります。用途やリスクによっては本格安全靴(S クラス)を選ぶ必要があります。
日本の現場での扱い : JIS / JSAAの運用ルールを再確認
- 日本の多くの工場・工事現場では、入場要件として JIS T 8101 合格の“安全靴”、または工程に応じた JSAA 認定シューズが指定されます。オーバーシューズでは要件を満たさない場合があるため、事前に社内規程や客先ルール(安全衛生規程)を必ず確認しましょう。
“産業機械を扱う工場”での選定ポイント(ドイツ製に興味がある方向け)
- 貫通&耐水 : 切粉・鋭利物や油がある環境では S3 (= つま先 200J+耐滑+耐貫通+耐水)がベース。湿潤床には SRC 滑り抵抗を目安に。
- ESD 対策 : 静電対策が必要な装置・ラインは ESD 対応表示を確認(EU も JIS も帯電防止規格が存在)。
- つま先素材 : アルミ / 樹脂は軽量で疲労軽減、鋼製は耐久に強み。現場の衝撃・圧迫リスクで選択。
- 運用ルール : 来訪者の短時間入場はオーバーシューズが便利ですが、常用者や高リスク工程はフル規格靴(例 : S3)を。日本の現場に持ち込む場合は JIS/JSAA 要件適合かを確認。
文化差の背景(なぜ違いが生まれた?)
- EU は「機能要件の組み合わせ(S クラス)」で柔軟に最適化できる設計思想。一方、日本は用途・材料・耐久に重きを置く JIS 体系と、軽快さを重視する JSAA という棲み分けが発達。来訪者対応や多国籍サプライチェーンが多い欧州では、着脱容易なオーバーシューズのユースケースが拡大しやすい構造です。
- EU : EN ISO 20345(S クラス)/ 日本 : JIS T 8101・JSAA で考え方が異なる。
- ドイツでは来訪者向けのオーバーシューズが実務的に活躍。ただしすべてが“安全靴”扱いとは限らない。
- 日本の現場に導入するなら JIS/JSAA 要件の適合確認が必須。
- 機械系工場では S3+SRC+必要に応じESD が選定の定番。
- ドイツ 安全靴
- EN ISO 20345
- S3 安全靴
- オーバーシューズ
- ビジター用安全靴
- JIS T 8101
- JSAA 規格
- 工場 安全対策
- ドイツ製 安全靴
- 産業機械 安全
- 滑り抵抗 SRC
- つま先保護 200J
- ヘルカベル
- HELUKABEL Japan
