ショート(短絡)とは?配線施工中に潜むリスクと、防止のためにできること
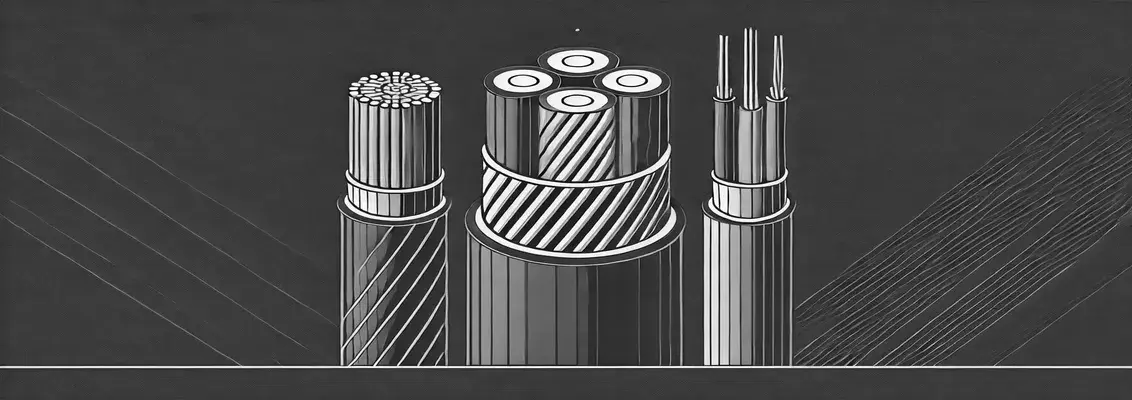
ショート(短絡)とは?
電気配線でよく耳にする「ショート(短絡)」とは、本来流れるべき経路とは別に、抵抗の低い経路で電流が一気に流れてしまう異常状態のことです。
たとえば下記のようなケースが典型的です。
- 異なる極性の導体同士(L と N、L と L)が直接接触してしまう
- 導体が金属筐体や接地された部材と意図せず接触する
- 絶縁が破れて、導体が水分・金属片などを介してつながってしまう
このような状態になると、設計値をはるかに超える大電流が瞬間的に流れ、ブレーカーが動作したり、最悪の場合はケーブルや機器の焼損、火災、感電事故につながります。
HELUKABEL の既存記事でも、絶縁材の役割は漏電やショートを防ぐこととして紹介されており、ショート対策における絶縁の重要性が強調されています。
なぜ配線施工中にショートが起きやすいのか?
ショートは、完成後の運転中だけでなく、「施工中」こそ発生リスクが高い現象です。特に以下のような要因に注意が必要です。
1. 絶縁被覆のダメージ・傷
- ケーブルを鋭利なエッジに擦りつけてしまう
- ケーブルを引き回す際に角張ったダクトで無理に引っ張る
- ナイフで被覆を剥く際に芯線に傷を入れてしまう
こうした小さな傷から、後になって湿気や振動、熱サイクルにより絶縁が破壊され、ショートや漏電を誘発します。絶縁体はショートを防ぐ最前線であり、適切な素材選定と丁寧な取り扱いが不可欠です。
2. 端末処理・圧着不良
- 圧着端子のかしめ不足・かしめ過ぎ
- 圧着方向の間違い
- 余分な撚り線が飛び出して隣の端子に触れる
端子台やコネクタまわりは、異なる極性の導体が近接する場所です。圧着不良や飛び出した撚り線は、運転中の振動や温度変化で位置が変わり、予期せぬショートを引き起こす原因となります。
3. ケーブル選定ミス・環境条件の見落とし
- 許容電流・電圧を満たさないケーブルを選定
- 耐熱性能が不足しており、長期的に被覆が劣化
- 油・薬品・紫外線に対して不適切な絶縁材を選択
環境に対して不向きなケーブルは、絶縁破壊やクラック→ショートにつながります。HELUKABEL では用途に応じた多様な絶縁材を用意し、それぞれの特性を紹介しています。( ケーブル絶縁体素材ガイド:各素材の特性と最適な用途を徹底解説 )
4. 保護導体・アースの未接続・誤接続
HELUKABEL の「 保護導体(アース線)の役割 」に関する記事でも説明されているように、保護導体はショートや漏電時に異常電流を安全に大地へ逃がすための重要な導線です。
- アース端子への接続忘れ
- アース線の誤配線
- 規格に反した色使いによる識別ミス
こうしたミスは、ショート時の感電・火災リスクを増大させます。
ショートが引き起こす具体的なリスク
1. 感電事故
ショートが起こると、筐体やフレームに危険な電位が生じる場合があります。保護導体が適切に機能していないと、作業者が触れた際に感電するリスクがあります。
2. 火災・設備の焼損
大電流が流れることで、ケーブルや端子部が急速に加熱し、被覆の発火・機器内部の焼損を招く場合があります。特に可燃物が近くにある配線ルートでは、火災への発展リスクを見逃せません。
3. 生産ラインの停止・ダウンタイム
- ブレーカーの度重なるトリップ
- 制御盤・インバータ・ロボットコントローラの故障
- 一部のショートがノイズ源となり、通信エラーが頻発
これらは生産停止や納期遅延に直結し、結果として大きな経済的損失を引き起こします。
ショートを防ぐための具体的な対策
ショート対策は、設計・施工・検査のすべての段階で積み上げる「総合力」です。
1. 設計段階でのポイント許容電流・電圧・環境条件(温度、油、薬品、屋外/屋内)を考慮したケーブル選定電源ケーブルと信号ケーブルの物理的分離、必要に応じたシールド採用ケーブル保護管・ダクト・トレイの材質やエッジ形状の検討余裕を持った曲げ半径・ルート設計
2. 施工段階でのポイント
- ケーブルの引き回し時に「引っ張り過ぎない」「こすらない」作業手順
- 専用工具・ストリッパーを用いた被覆剥き
- メーカー推奨の圧着工具・ダイスを使用した端末処理
- 端子台での配線整理(ラベリング・束ね方・余長処理)
3. 検査・メンテナンス
- 絶縁抵抗測定による施工後チェック
- 熱画像による過熱箇所の確認
- 定期点検時の端子増し締め・目視検査(変色・ひび割れ・変形)
4. 保護導体・保護機器の正しい活用
- 保護導体(アース線)の確実な接続と色識別(緑/黄色)
- 適切な遮断器・漏電遮断器(RCD)の選定と試験
- ショート時の影響範囲を最小化するための回路分割
HELUKABEL のケーブルでショートリスクを低減する
HELUKABEL グループは、ドイツ・Hemmingen(Stuttgart近郊)に本社を置くケーブル・電線およびケーブル付属品の国際的な大手メーカー&サプライヤーです。世界 43 カ国に 76 ヵ所の生産拠点と営業所を展開し、産業・インフラ分野のお客様に電気接続ソリューションを提供しています。
ショート対策という視点で見ると、HELUKABEL のケーブルには次のような強みがあります。
1. 用途に応じた絶縁材・シース材の選択肢
- PVC、PE、XLPE、TPE、電子ビーム架橋絶縁材など、多様な素材ラインアップ
- 高温環境、油・薬品環境、屋外・紫外線に強いタイプなど、用途別に最適化された設計(記事 10 ケーブル絶縁体素材ガイド:各素材の特性と最適な用途を徹底解説)
これにより、環境に起因する絶縁劣化やショートを抑制することができます。
2. 保護導体・シールド構造を備えた設計
- 緑/黄ツイストの保護導体(アース線)を内蔵したケーブル構造
- 銅編組・箔シールドによるノイズ低減と、異常時の電流経路の確保
特に大型機械やインバータ駆動モータなど、高調波・ノイズが多い現場では、シールド付き・保護導体付きケーブルがショート・ノイズ対策の要となります。
3. グローバル規格と試験設備に基づく品質
- 国際規格(IEC / EN 等)準拠の試験設備と品質管理
- 耐熱・耐油・耐機械的ストレスなど、厳しい条件での検証
これらにより、長期にわたり安定した絶縁性能を維持し、ショートリスクを低減します。
まとめ : ショート対策は「見えないところ」への投資
ショート(短絡)は目に見えない配線の中で起こるため、異常が起きてから初めて存在に気づくことが少なくありません。しかし一度発生すれば、感電・火災・設備停止といった重大な結果につながります。
- 設計段階でのケーブル選定
- 施工段階での丁寧な取り扱いと端末処理
- 検査・メンテナンスの継続
- 保護導体と保護機器の正しい活用
これらを組み合わせることで、ショートリスクは大きく低減できます。
HELUKABEL は、ドイツ本社の技術力と、日本のお客様向けの情報発信・サポートを通じて、安全で信頼性の高い配線システムづくりをサポートします。ショート対策やケーブル選定でお困りの際は、ぜひ HELUKABEL Japan にご相談ください。
